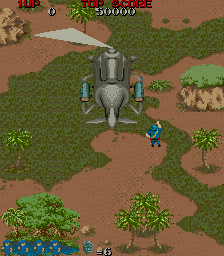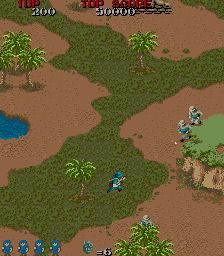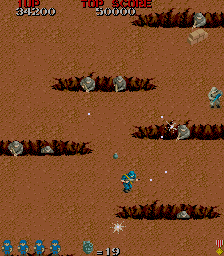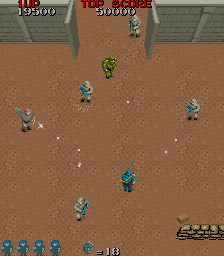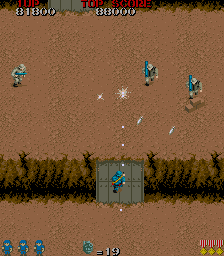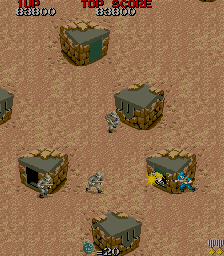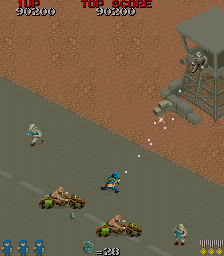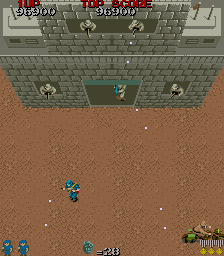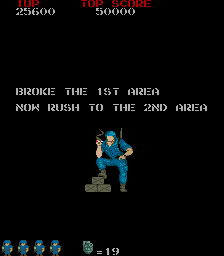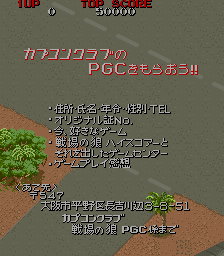題目:戦場の狼
 |
■メーカー:カプコン ■メディア:アーケード ■ジャンル:シューティング ■発売年 :1985年 |
| 「孤独に戦場を駆ける兵士」という意味合いでのタイトルなんだろうけれど、狼とは本来群集生活を営む動物。 従って、正しくは『戦場の一匹狼』なのでは…。 |
最も現実的な夢
| 本作の舞台は、タイトルの示す通り 「戦場」。砲弾が跳び交い、兵士達が 血みどろの戦いを繰り広げる修羅場で ある。妄想とご都合に満ち溢れた魔法 の世界や、科学文明に過剰な期待の寄 せられたSFの世界とはこの時点で違 うことが見て取れよう。 何しろ、「戦場」とはこの現実世界 において、人類発足以来途切れること 無く繰り返されている事象。文明の発 達とともにそれは激化し、被害や犠牲 者も増加を辿る一方。今では最早、そ の軍事力に人類自身が責任を持ち切れ なくなるまでに肥大化してしまってい る――今はこの話は置いておこう。 |
|
|
ともかく、「戦場」即ち「戦争」とは、こ の現実世界において常に展開されている(悲 しいけれど)。実際に起こっている・起こり 得ることであるだけに、創作のテーマとして は現実味があるわけである。そういうものを テーマとして扱えるのって、世が平穏である 証なんだろうなあ…。 この日本国内においても戦争の実体験者は 今や一握りとなったが、たとえ非体験者であ れ、戦争が極力(「断固」とは言わん)避け たい道であることは感じていよう。「サバイ バルゲームみたいな『ごっこ』はともかく、 実際の戦争はごめん」という見解も多いし、 せめてそういう気持ちは持っておきたいもの である。 |
| 本作『戦場の狼』は、そんなハードな現実世 界を舞台として起用したわけである。当時のゲ ームはどれもこれも、SFやファンタジーとい った「そのゲームなりの世界」で個々に完結し ていたので、こうした地に足の着いた世界は逆 に新鮮であった。 この数年前に公開された『ランボー』や、こ の頃から徐々に流行の兆しを見せていたサバイ バルゲームの影響からか、作品は大ヒット! 反戦平和はもちろんとして、戦場をたった一人 で突き進む孤高のソルジャーってやっぱカッコ イイしな~。善悪云々を問わず、大勢で一人を 攻撃するのは「卑怯」のイメージが付きまとう が、逆に一人で大勢を相手に戦うのは格好良く 思えるから不思議である。 |
|
本能(本音?)の解放
| そんなゲーム世界の雰囲気もさることながら、肝心要のゲーム性はもちろん秀逸であった。初期の ゲームだけに、操作系は8方向レバーにボタン2つと極めてシンプル。ただこれだけのシステムで大 ヒットに繋がったのは、そのシンプルさがゲーム世界にマッチしていたからではないだろうか。 |
| このゲームはプレイヤーの進 行に合わせて画面が動く任意ス クロール制。そしてゲームシス テムにおいて「とにかく前進」 という明確な方向性があった。 当然、ゴール地点であるステー ジの行き止まりを目指して進む わけであるが、冒頭で何度も語 った様に舞台は「戦場」。そこ らかしこらで激しい銃撃戦が展 開され、一瞬の油断が死へと繋 がる「地獄」である。そのテー マに違わず、画面内は大勢の敵 兵や銃弾で埋め尽くされ、プレ イヤー目掛けて四方八方から攻 |
|
め寄せて来る。本当、息つく暇 なんか全然無いくらい…。 そんな熾烈極まる修羅の旅路 を、プレイヤーはたった独りで 駆け抜けなければならないので ある。マシンガン一丁と手榴弾 だけを頼みに…。このシチュエ ーション、男なら燃えずにはい られまい! ゲーム中は主人公 たるスーパー・ジョーにシンク ロして、ほとんどトランス状態 である。死地に赴く孤高の戦士 ってのに憧れるのよ、男って生 き物は…。 |
|
そして何より大きいのが、やはりその爽 快感であろう。プレイ中はアレコレ難しい ことは考えず(考える暇も無いけれど)、 頭の中を真っ白にしてゲームにのめり込め る! 敵からの熾烈な攻撃に神経を磨り減 らす反面、群がる敵をマシンガンでバリバ リ撃ち倒すのは何とも痛快である。4~5 人固まっているのを手榴弾でまとめて吹っ とばすのなんて胸の空く思いよ、本当♪ 昔の子供の戦争ごっこ、そしてサバイバル ゲームの醍醐味は多分ここにあるんだろう なあ。 実際の戦闘では「死」というリスクとの 背中合わせだけれど、創作の世界にはそれ が無い分、「快感」の部分だけを満喫でき るからかも知れない? |
| そもそも人間には「闘争」「破壊」「殺戮」な どの本能がある。それら「負」属性の事象を、普 段は「理性」というやはり人間特有の事象によっ て抑えているわけである。「理性」の限界を超え た者、あるいは「理性」のカケラも無いバカども |
によって、暴力や破壊活動、果ては殺人といった 陰惨な事件が引き起こされるということ。そうい うことの無い社会を築くためにも、人間社会では お互い譲り合い認め合い、昔みたいに子供にしっ かりと道徳教育をしていかなければ…。 |
| しかし、理屈云々でなく感覚的 に、人間が「暴力」「破壊」とい うものに快感や魅力を感じてしま うのも確か。無意味無差別にその 行為に及ぶのはもっての他だが、 何かの拍子にそれが噴出してしま う恐れもある。そのガス抜きのた め、そして無罪者に向けられかね ない照準を逸らすために、人はそ れ用のルールを制定した。刃を思 い切り落とし、規定に則った上で お互い納得ずくでの暴力――それ がご存知「格闘技」であり、そし てサバイバルゲームや戦争映画み たいな「ごっこ」なのであろう。 |
つまりはこれらのおかげで、人間 社会は不条理な暴力の横行を抑え られていると言える。これは揺る ぎなき事実である。 逆に、何でもかんでもミソクソ に「暴力はダメ!」で禁じてしま ったら、発散できない鬱憤によっ て逆に暴力行為が横行しまくるの は必須である。一見好ましからざ るものでも、それが無ければもっ とマズイことになるという「必要 悪」ってものがあるのよ、世の中 には。PTAとかの「お子様はお 宝」団体は、その辺を理解しよう としないから困るよなあ、本当。 |
|
|
ともあれ、『戦場の狼』というゲームの世界は、人間の 有する戦闘系のパッションをビシバシ刺激してくれる! かなり昔の作品ではあるが、その当時においてさえも戦場 の厳しさや激しさが伝わってきたもの。銃弾の嵐を掻い潜 るのにはヒリヒリした緊張感を伴うし、昨今のSTGのバ カみたいな弾幕避けのストレスとは大違いである。そして やはり、マシンガンをぶっ放しながらズンズン進撃するの が何より気持ちいい! 後の『ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド』シリーズ然り、 「闘争」「破壊」「殺戮」ってのは本能に直結する快感だ わ、本当。それ系の作品がジャンルを問わずヒットをとば しているのも、人が法治社会で生きつつも「負」の感情の 発散を求めていればこそかもねえ。誰だってたまにはハメ を外して壊れてみたいし…。いわゆる「エリート」ほど、 これ系作品を求める傾向があるんじゃない? |
ぼくたちの戦場
筆者の本作との出会いは小学生の頃。県下最大のスケート場(既に閉鎖…)のゲームコーナーでのことであった。
| いくつものテーブル筐体の並ぶ中、 妙に際立って見えたゲームが本作『戦 場の狼』であった。 他のゲームが戦闘機とかを操って空 や宇宙が舞台だったのに対し、本作は 地上戦で人間キャラが主役。身近に感 じられるグラフィックや人間臭く立ち 回るキャラ達に、奇妙な親しみを覚え たものであった。 この頃は既に「夢の世界」と決別し (「見限った」のではなく「割り切っ た」)、現実的なものに魅力を感じる 様になってきていたからかと思う。何 しろ、当時愛好していたTVドラマが 『西部警察』だったくらいだし^^ |
|
|
それにやはり、たった独りで戦場を突き進む兵士の姿
にはカッコよさがあった。気の弱い子供であった筆者だ けに、自分に無い「強さ」「勇気」を持った存在には無 意識に憧れを抱いてしまう様である。幼少時は特撮ヒー ロー、現実に目覚めてからは格闘家や戦士という風に。 実際、主人公のスーパー・ジョーは、数々の死線を潜り 抜けて勝利してきた英雄なのだから尚更であった(『ヒ ットラーの復活』では捕まっちゃうけれど^^)。 戦争が好ましからざる事象だってことはもちろん承知 していたけれど、それはそれとして「戦士」という存在 にはやはり理屈で説明できない魅力があるんだよねえ。 使命感を背負って戦う者はやはりカッコイイ! 自分も そうしたヒーローを目指して頑張った時期があったけれ ど(「雑誌投稿」という舞台で)、果たしてなり得たで あろうか…。 |
|
シンプルなゲームシステムと現実味のある世界観が絶
妙に調和し、人間の本能的快感を刺激することで大人気 となったと言える『戦場の狼』。キャライメージがまず 先行(グッズや同人ウケ狙いなんだろうなあ)し、ハー ド性能による「演出」で表面的な水増しばかりの近年作 とはまるで逆である。当時のハード性能で、優れたゲー ム性と魅力的な世界を描こうとしている姿勢が伝わって きていいなあ。 このゲームは、ゲーマーの主要年齢層である児童らにこ そプレイしてもらいたい! 至れり尽くせりの新設設計 を当たり前に享受している世代に、昔のゲームの厳しさ と本質的な面白さを噛み締めてもらいたいから。ゲーム でも現実でも、太平の世に浸ってきた者が戦場に踏み込 んだら即死するかも知れないが…。 |
|